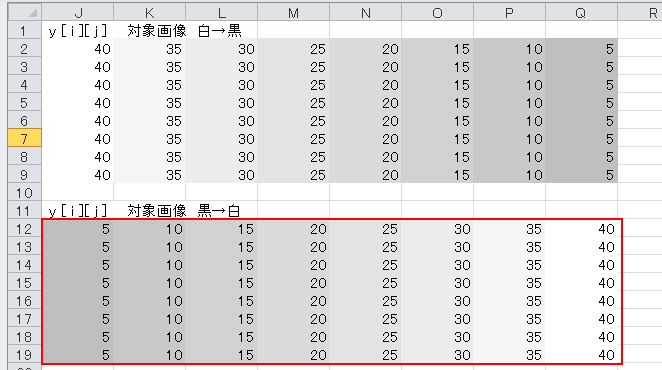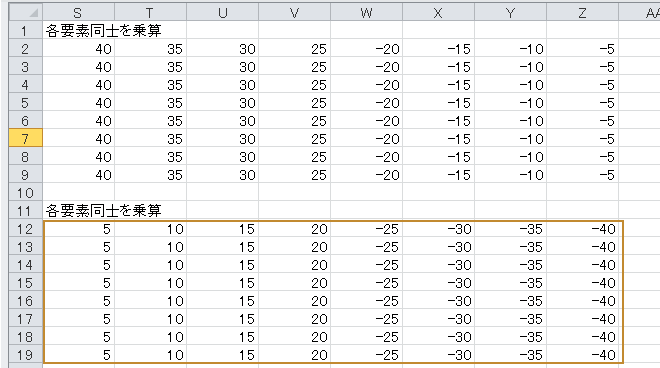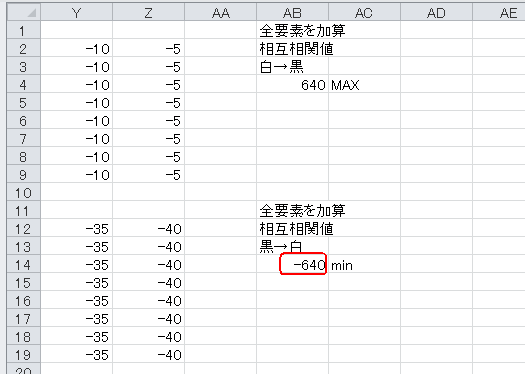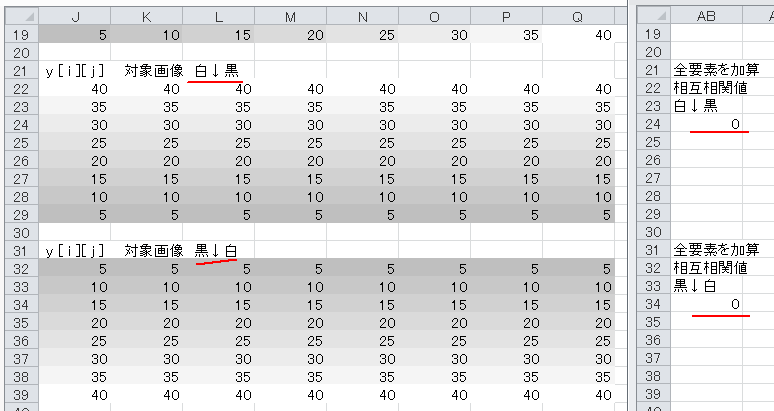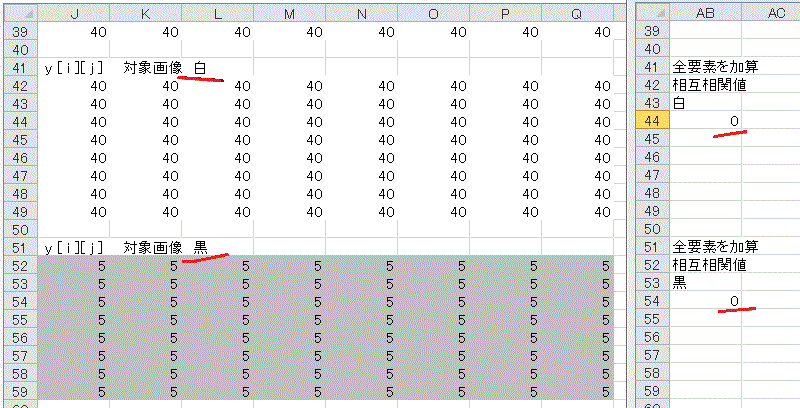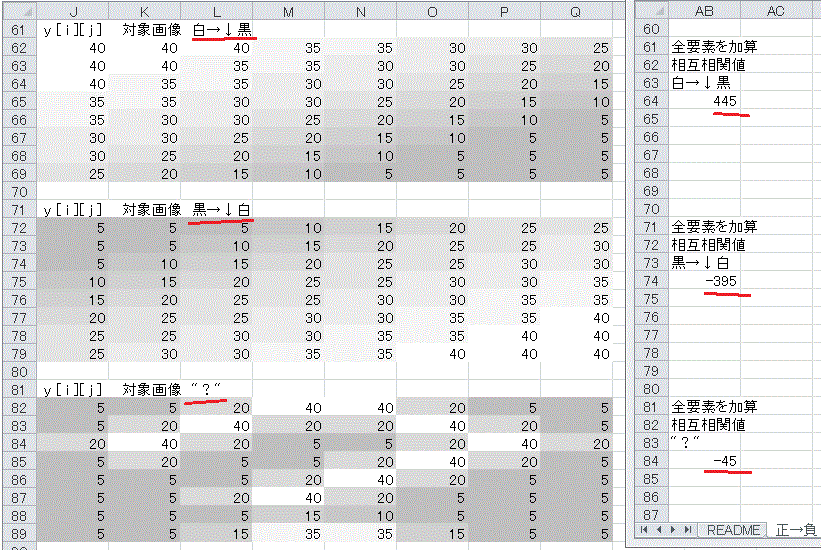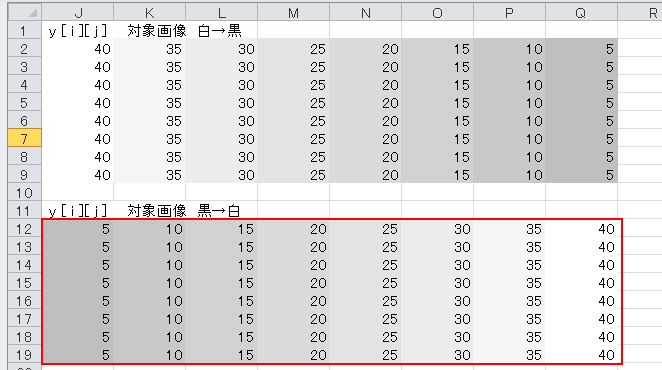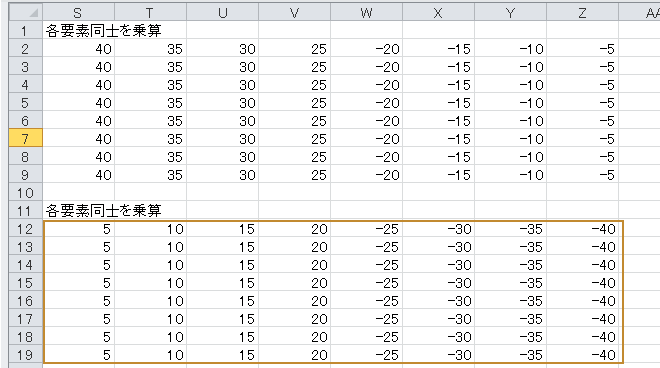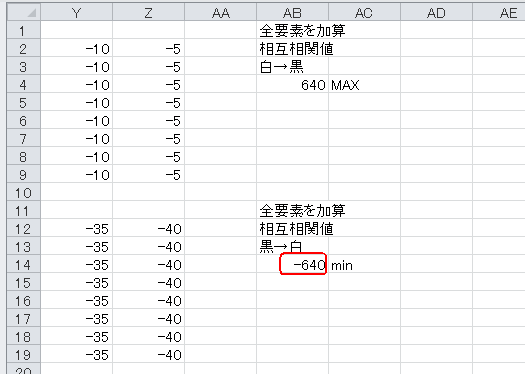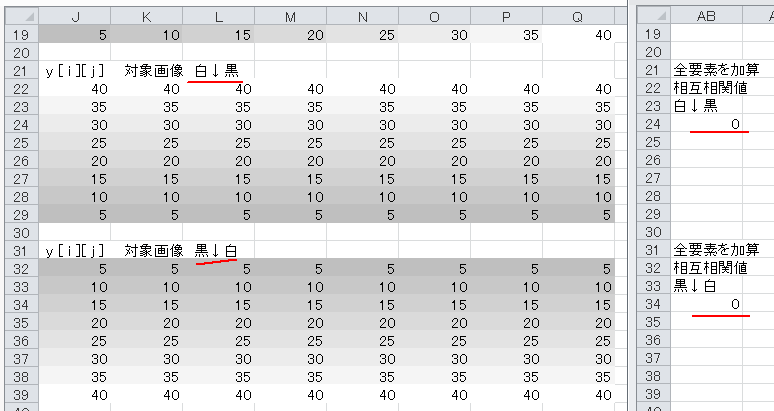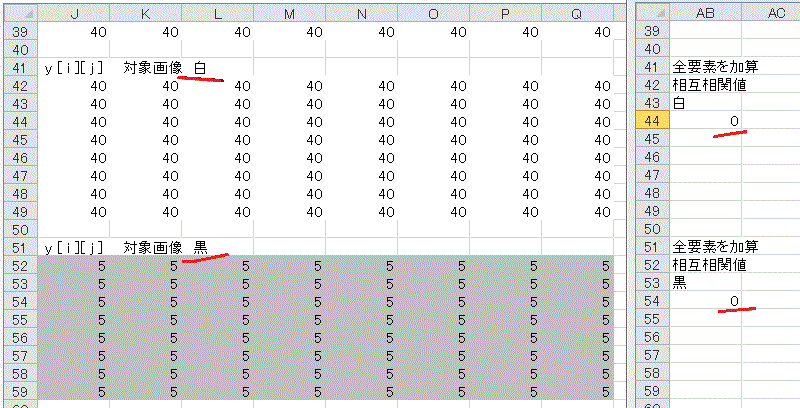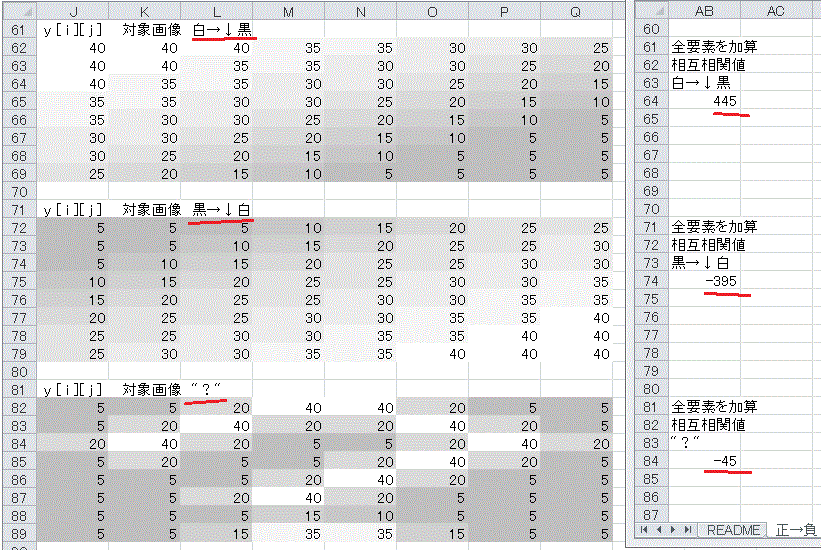5-04 相互相関を画像に適用する(続き)
●次は左から右に白くなる画像を対象にする
対象画像「白→黒」の下に「黒→白」があります(図5‐58)。右に行くにつれて画素値が大きくなっています。 |
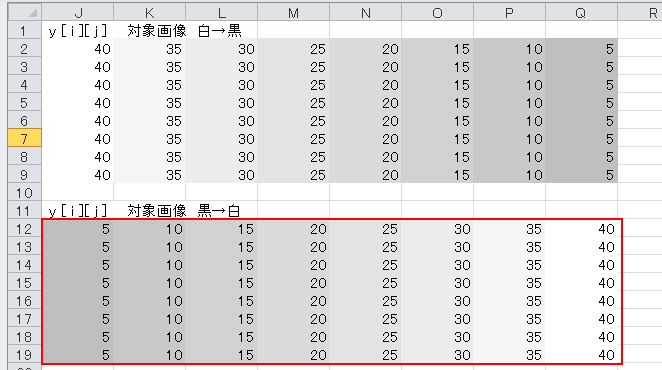
図5-58 12行目以下を見る
●プラスは小さな値、マイナスは大きな値
その右、S〜Z列に乗算結果があります。テンプレートの右半分が-1なので、右の方は負の大きな値になっています(図5‐59の赤枠内)。 |
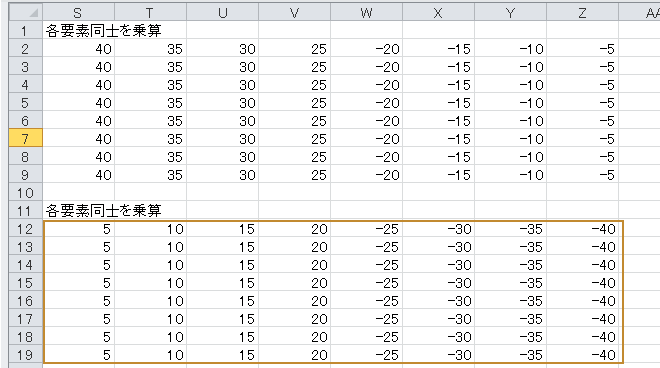
図5-59 12行目以下に乗算結果
●テンプレートとは真逆の相関があるということ
一番右のAB列に相互相関値があります(図5‐60)。上図の乗算結果を見ると負の値が支配的なため、足し込んでいくと負の大きな値(極小値)になります。 |
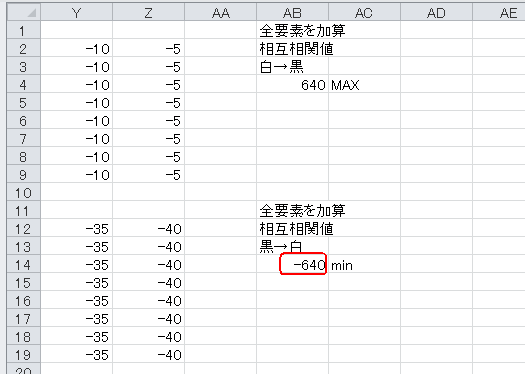
図5-60 AB列14行目に相互相関値
●変化の方向が「直交」しているケース
その下(21行目以下)は「白↓黒」(上から下に白から黒)、さらにその下に「黒↓白」があります。テンプレートは左から右に変化するので、上下に変化しても「相関なし」、すなわち相互相関値は0になります。 |
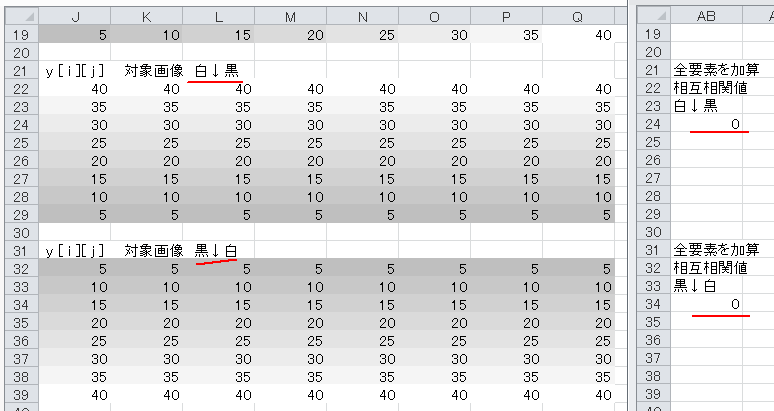
図5-61 対象画像3つ目、4つ目の相互相関値
●変化がない画像だとどうなるか
41行目からは白(一色)、51行目からは黒(一色)になります。テンプレートとは相関がないということで相互相関値は0になります。 |
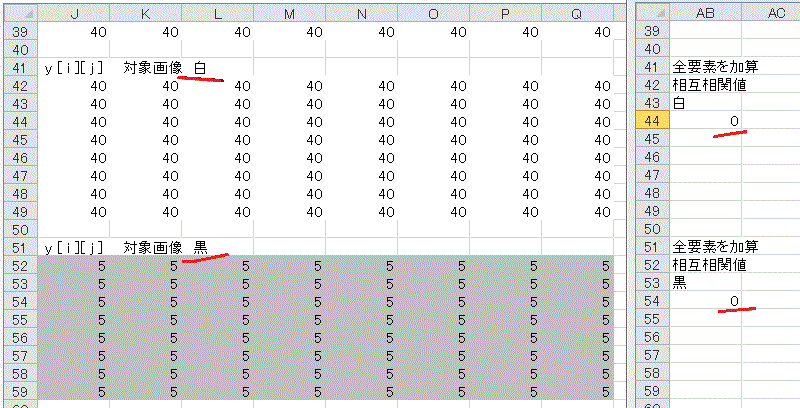
図5-62 真っ白画像、真っ黒画像の相互相関値
●少し相関がある、少し逆相関がある、ほとんど相関がないケース
61行目からは白→↓黒(右下に向かって黒くなる)、71行目からは黒→↓白(右下に向かって白くなる)になります。前者はテンプレート(正→負)と多少相関があって相互相関値は正の値、後者は逆相関が多少あるので相互相関値は負の値になります。
81行目"?"はテンプレートとはほとんど相関はないようで、相互相関値は負の小さな値になります。 |
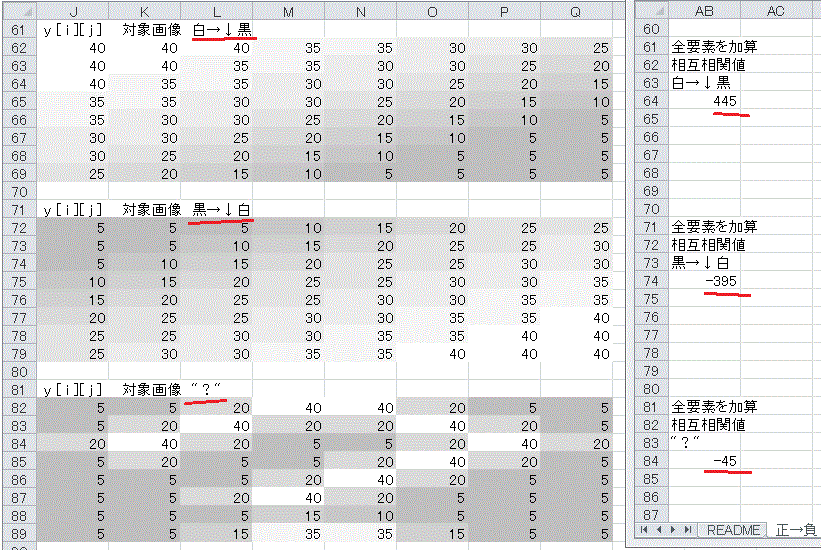
図5‐63 テンプレート「正→負」とどれくらい似ているかということ
次のページへ
目次へ戻る |